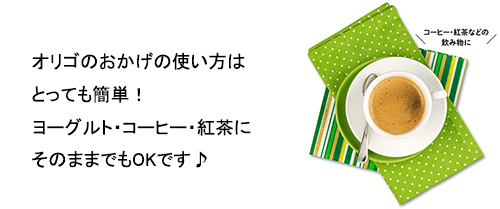子供に白湯におりごのおかげをいれて飲ませました!いつもなら白湯は全く飲んでくれず水分補給は母乳だったのですがおりごのおかげと一緒だと飲んでくれました\(^o^)/暑い夏なので水分補給で飲ませたいと思います!他にもヨーグルトにいれてたべてとても美味しかったです(^^)美味しくたべてビフィズス菌も増えて良いと思いました!これからも続けていきたいと思います!
投稿日時:2012/08/08 : ![]() Sachan★まま
Sachan★まま

『オリゴのおかげ』モニプラ支店ファンサイト参加中リオリオは1週間に1度しかをしませ~んしかもする時顔は真っ赤にして泣き出しちゃうの…見てて可哀想でも「オリゴのおかげ」でモニター当選して使ってみたら2日に1回になって本人も楽になったみたい美味しいし私もついでに便秘解消
投稿日時:2012/08/07 : ![]() るきりお☆パラ...
るきりお☆パラ...

モニプラさんより当選した商品「オリゴのおかげ」。妊娠中の為、特に安定期の中期に入ってからお腹の調子が段々悪い方向へ先生から薬を処方してもらって、何とかやっている状態でしたが、できれば食べ物でお腹の調子を良くしたいと思っていたところで当選できたのでラッキーでしたこれ、使っているのと使わないのとではお腹の調子が全然違いました「オリゴのおかげ」は、パッケージの通りビフィズス菌を増やしてくれる商品です。では、なぜビフィズス菌がお腹にいいのかというと…赤ちゃんのウンチが、黄色くて酸っぱいニオイがすることを知っていますか...
投稿日時:2012/08/07 : ![]() まいのLife is ...
まいのLife is ...

オリゴ糖ってみなさん摂っていますか?お腹に大切なビフィズス菌を選んで増やすのがオリゴ糖。腸内のビフィズス菌は人によってそれぞれ違うのだそう。ビフィズス菌は生まれてすぐの私たちの腸内で増え始め、腸の調子を整えてくれています。人にとってビフィズス菌は大切な細菌(善玉菌)なのです。私は毎日の健康習慣のために「オリゴのおかげ」を摂取しています!これはとっても摂りやすいんですよ。スプーンでそのまま頂いてもOKガムシロップのような透明の液体です。私は毎日コーヒーを飲むのでコーヒーに入れてみましたよ。味は普通のシロップと変わらなくて...
投稿日時:2012/08/07 : ![]() Himawari の Ha...
Himawari の Ha...

突然ですが、わたくし便通は悪くないと思います。まっ、たま~に一日出ないことや下痢っぽくなることもありますが。こんな記事をチラッとみまして…子供の腸...
投稿日時:2012/08/07 : ![]() 暇人の日記 - ...
暇人の日記 - ...

最近、お腹の調子がいいのは「オリゴのおかげ」なんです!!もともと便秘ぎみだったんですが、妊娠してから悪化してしまいまして…一時期は、処方してもらった...
投稿日時:2012/08/07 : ![]() … RA SI DO … -...
… RA SI DO … -...

モニプラさんで、オリゴのおかげのモニターをさせていただきました。おなかのなかのビフィズス菌をふやして、お通じをよくするオリゴ糖。毎日小さじひとさじぶん舐めたり、ヨーグルトにはちみつがわりに入れて食べたりしたら、お通じが少し改善されました。口当たりもまろやかで、はちみつと水あめを足して二で割ったような感じです。お通じに悩む人はぜひ!おすすめです。『オリゴのおかげ』モニプラ支店ファンサイト参加中
投稿日時:2012/08/07 : ![]() そらいろのたね
そらいろのたね

もう3週間くらい前になるかなぁ?以前から気になっていた『オリゴのおかげ』が届きましたこれね、おなかの中にいる自分自身のビフィズス菌を増やして、おなかの調子を整えるプレバイオティクス食品しかも妊娠中、授乳中でも気にせず食べられる私、普段からほとんど便秘をする事が無かったんだけど…マッキーを妊娠してから便秘に悩まされ、産後もやはり便秘は治らず。。。授乳中だから薬は飲めない…飲めても飲みたくないしで、水分を沢山取るようにしたり、繊維の多い野菜を取るようにしたりして努力してたんですけど、なかなか思うように改善され...
投稿日時:2012/08/06 : ![]() KeiKou党の男の...
KeiKou党の男の...

『オリゴのおかげ』モニプラ支店ファンサイト参加中毎日使うことで、便秘はだいぶ良くなった!朝舐める習慣にして、旅行中も舐めてたよ。パンやホットケーキに使っても、美味しかったし、大学芋も簡単にできた!洗米汁乳酸菌は、なんかうまくいかなくて…ダメだったのが残念。。iPhoneからの投稿
投稿日時:2012/08/06 : ![]() まきのブログ
まきのブログ
特定保健用食品 『オリゴのおかげ』650g(シロップタイプ)
本物のトクホのオリゴ糖の効果を、是非皆さんのおなかで実感してください!
【許可表示:乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つと食品です】という表示が許可された甘味料です。
摂取上の注意
●摂り過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。
●多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。