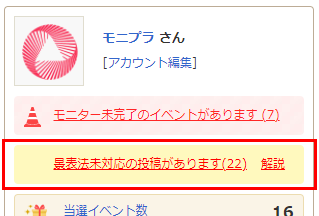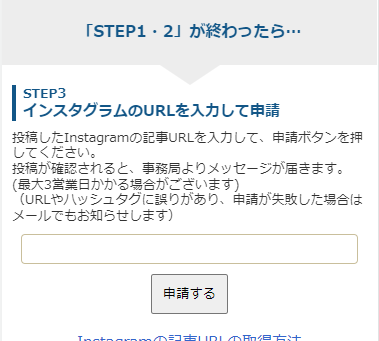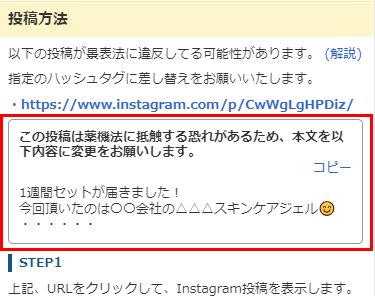景表法改正に伴うおねがい
『ドトールコーヒーファンサイト』
アクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ございませんが、当ファンサイトは
モニプラ内でのサービスを終了させていただいております。
終了したイベント、モニターに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
| お問い合わせ先 |

|
株式会社ドトールコーヒー |
|---|
注目の無料モニター・サンプル情報はコチラ!
期間限定・新商品「ミラノサンド」★第5弾★無料モニター300名大募集!!
二価鉄触媒
二価鉄触媒は、産業廃棄物の脱臭の為に開発されました。
その二価鉄触媒に、多種の触媒を入れ相乗効果をもたらしたのがホルムキラーです。
http://www.touwasangyo.jp/syousyuu.html
新触媒ホルムキラーの特性
消臭・吸着塗料としての特許製品と、特許特殊セラミックスの抗菌性特性を兼ね備えた商品です。触媒反応も相乗効果があります。
消臭機能、帯電防止機能、抗菌機能、防汚機能に優れています。有害物質を含まない人体に安全な多機能素材です。超撥水性、超親水性を、ともに持っていますから、カビの原因と汚れを防ぎます。
FC1をFC0合板の濃度基準以下までに分解吸着します。
新触媒「ホルムキラー」の作用
新触媒「ホルムキラー」は硫酸第一鉄水溶液にEDTAを添加することで、第一鉄のキレート化合物が生成している。「ホルムキラー」はほぼ中性の水溶液中で鉄イオンが鉄キレートとして安全化されている。
その上に、無機成分(例えば、チタン、シリカ、アルミニウム、マグネシウムセピオライト、ゼオライトなど)を分散域は、溶液状態で混合使用できる安定で、安全な物質である。
1)酸化還元現象
鉄化合物には酸化還元性があり、第一鉄化合物は、本来還元性であり、自らは酸化され第二鉄化合物になる。
2)緩衝現象
捕集された悪臭が、塩基性・酸性に応じて、それを中和して消臭する。「ホルムキラー」は緩衝作用があって複雑なイオン平衡によってPh値は急激に変わらない。以上の機能は、単独、又は他の無機成分と相乗作用として、効果を示すものである。
http://www.touwasangyo.jp/baria.pdf
http://www.touwasangyo.jp/horumukira-omote.pdf
2007年10月11日
ノーベル化学賞に独研究者 触媒表面の化学反応解明
スウェーデン王立科学アカデミーは10日、07年のノーベル化学賞を独マックス・プランク研究協会フリッツ・ハーバー研究所のゲルハルト・エルトゥル氏(71)に贈ると発表した。
授賞理由は「固体表面の化学反応過程にかんする研究」。化学反応を促す働きのある触媒の詳細な研究を中心として、固体表面化学への貢献が評価された。
エルトゥル氏は、たとえば化学肥料の原料アンモニアの合成で使う鉄触媒や、車の排ガス浄化に使う白金触媒の表面で起きている原子や分子のふるまいを、独自に開発した手法で解明することに成功した。
その後、固体表面化学の研究は、燃料電池の開発やオゾン層の破壊過程の解明、バイオ燃料の合成など、化学工業から環境科学、ナノテクノロジーまで多くの分野にすそ野を広げてきた。
もう少し化学っぽい言い方をすれば特に大きな業績が2つ。
1つはハーバー・ボッシュ法(N2+3H2→2NH3)における酸化鉄触媒表面上での窒素や水素の分子機構を解明しました。肥料の原料となるアンモニア製造法に対する理論付けになり、この貢献に対してノーベル賞が贈られることになりました。
もう1つは一酸化炭素の触媒的酸化反応で、パラジウム触媒表面で二酸化炭素へと酸化される反応の分子機構を研究しました。この成果は自動車排ガスの浄化技術の発達にも貢献しています。
なお、紫外光電子顕微鏡(UPM)や、走査トンネル顕微鏡(STM)を駆使して、触媒表面上の振動現象を明らかにした点が偉大なようです。
転載
スウェーデン王立科学アカデミーは6日、2010年のノーベル化学賞を根岸英一・米パデュー大学特別教授と鈴木章・北海道大学名誉教授ら3氏に授与すると発表した。高血圧症の治療薬や液晶材料など多様な工業物質の製造に必須の合成法を開発したことを評価した。(中略)共同受賞するリチャード・F・ヘック米デラウェア大学名誉教授ら3氏への授賞理由は「有機合成におけるパラジウム触媒クロスカップリング」。医薬品や電子材料など様々な工業物質を効率よく合成する革新的な手法である「クロスカップリング反応」を開発した。(引用:日本経済新聞)
"クロスカップリング反応"とは何か?
炭素と炭素をつなぐ化学反応は、有機化学という学問を根底から支える化学反応です。有機化合物=炭素を含む化合物として、そもそも定義されているからです。炭素原子どうしをつなぐ反応が無ければ、有機化合物をつくることは出来ず、もっと言えば、有機化学という学問自体がそもそも成り立たないとほどです。
つまり【有機化学で最重要な化学反応=炭素同士をつなぐ反応】、だといえます。
有機化学の歴史は、実に100年以上のものがあります。今日ではその進歩は目覚ましく、知られる化合物であればほとんどどんな形のものでも作れてしまうほどの発展を遂げています。
しかし意外なことですが、『亀の甲』としておなじみの構造・『ベンゼン環』同士の炭素を自在につなぐことが可能となったのは、実はここ30年での出来事です。これを自由度高く行える手法こそが、"クロスカップリング反応"として知られている化学反応なのです。
カップリング反応とは、「2つのものを結合させる化学反応」の一般名称です。異なる二つのものがくっつく反応の場合、特にクロスカップリング(cross coupling)と呼んでいます。(※結合するものが同じ反応であれば、ホモカップリングと呼ばれます)
クロスカップリングに欠かせない金属、パラジウム
炭素同士をつなぐ反応は、極論すればいずれも「プラスとマイナスをつなぐ」という見方で捉えることが出来ます。脱離基を持つ化合物(芳香族ハライド)などがプラス、炭素-金属結合をもつ化合物(有機金属化合物)がマイナス単位の代表例となります。
ただし、ベンゼン環化合物の場合は事情が特殊で、プラスとマイナスの両者を混ぜるだけでは反応が進行しない―つまり結合をつくることができません(置換反応に不活性)。
こういった反応を進行させるためには、"触媒"と呼ばれる物質、つまり「反応を仲立ちして加速させる物質」を少量混ぜてやる必要があります。
このクロスカップリング反応への触媒として有効だったのが、パラジウムという金属です。なぜパラジウムが良かったのか?―コレを書き始めると、やや長くなってしまいます。速報ですので今回はひとまず、『パラジウムという金属がクロスカップリングの触媒としては欠かせないものだったんだ』という天下り的理解でとどめておきましょう。
ちなみにパラジウムは周期表のここ(↓)です!
さて、「クロスカップリング」でまとめて授賞となった3氏は、それぞれどのような貢献をしたのでしょうか?―踏み込み始めるとやはり長くなるので、速報ではざっくり解説するにとどめます。
上で記したクロスカップリングの一般式をもう一度ご覧ください。
ここで使われている"マイナス炭素源"が、開発した化学者ごとに少しずつ違っているのです。
たとえば根岸教授は亜鉛(Zn)やアルミニウム(Al)、鈴木教授はホウ素(B)、ヘック教授は二重結合(金属不要!)をメインに活用し、それぞれの立場からクロスカップリング反応の発展に貢献しました。
これらの化学反応はいずれも、化学合成のパラダイムシフトを起こすほどのインパクトある反応として発展してきました。
この開拓的偉業に敬意を表し、現代ではそれぞれの化学反応に、開発者の名前が付けられています。つまり、それぞれが根岸クロスカップリング、鈴木(-宮浦)クロスカップリング、溝呂木-Heck反応という人名反応として定着しているのです。今ではワールドワイドで通じる名称となり、鈴木・根岸の名前は、世界のあらゆる化学界で知られるところとなっているのです。
ベンゼン環をつなぐことで初めて生みだされる有用物質
「ベンゼン環を自由につなぐことは30年前まで事実上不可能だった」と述べました。逆にいえば、こういった手法が発展したことで、それまでつくることすら不可能だった、世界に役立つ物質をつくれるようになった、ということでもあるわけです。 クロスカップリングで初めて供給可能になった有用物質(医薬品や化学材料)の例を、いくつか下にあげておきましょう。もちろんこれらはほんの一角であり、これ以外にも沢山、人類に役立つ化合物が、クロスカップリング反応を用いて生み出され続けています。
(赤色が連結型ベンゼン環、青ハサミで示した箇所が、クロスカップリング反応で繋がれる炭素結合)
まとめると、これらの3氏の業績は、ベンゼン環などの「炭素をつなぐ」ための新たな化学反応(クロスカップリング)、およびそのための触媒(パラジウム触媒)を開発し、これまで合成が事実上不可能だった有用物質(医薬品や機能性材料)を効率的にかつ自由度高くつくりだすことに成功した、ということです。
もっとざっくり言ってしまうと、月並みな表現になってしまうかもしれませんが、
【化学の考え方や、研究世界を変えてしまうほどのインパクトがある、不可能を可能にする化学反応を開発した】
ということが、ノーベル化学賞に選ばれた理由になります。
鉄触媒を用いるクロスカップリング反応など、有機金属化学種をもちいた斬新な合成反応の開発に取り組んでいる。
http://monipla.jp/bl_rd/iid-5229495134dd9f8ba735ef/m-4d6b812fde81e/k-1/s-0/
今日のモニプラです!
期間限定・新商品「ミラノサンド」★第5弾★無料モニター300名大募集!!
当選しました!!
お昼ご飯獲得!!
美味しそうです。
柳ヶ瀬に行こうかな?岐阜駅にもあるね。何処にしよう!!
商店街応援しているので、大型店には行かないよ。
岡田氏は以前嫌いじゃ無かったけれど、イオンの一人勝ちは、許せない。
大型店法の兼ね合いもあるし。
ずるくない?
otuta 2011-06-07 08:47:30 提供:株式会社ドトールコーヒー
| Tweet |
メニュー

企業紹介
株式会社ドトールコーヒー
ドトールコーヒーは、コーヒー豆の輸入、焙煎加工並びに卸売販売および、飲食店の経営やフランチャイズ事業を展開しています。
主な店舗展開は5つの業態「ドトールコーヒーショップ」「エクセルシオール カフェ」「カフェ・マウカメドウズ」「カフェ・コロラド」「ル・カフェ ドトール」です。