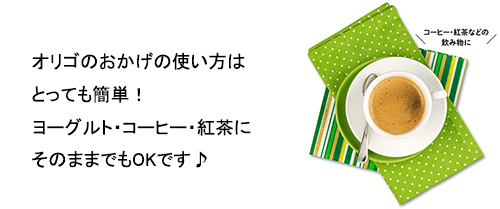オリゴのおかげサイズは130gミニボトル(お1人で約2週間分)300gレギュラータイプ(お1人で約1カ月分)←上記写真はこちらです市販のドレッシングサイズな感じですよレシビ集も含めてパンフレットが一緒についてきましたまずは・・・オリゴのおかげを舐めてみました思っていたよりは甘すぎなくて、これだけでもおいしいもっとドロッと水あめみたいかな、と思っていたのですが、水あめよりもゆるい感じでしたちなみにカロリーはお砂糖の約半分だそうですこれはありがたいですよね〜子供達が食べやすいようにと思い、『ヨーグルト&桃缶』にかけてみました子供達は自...
投稿日時:2011/07/23 : ![]() しぃちゃんのに...
しぃちゃんのに...

『オリゴのおかげ』モニプラ支店ファンサイト応援中腸内のビフィズス菌を増やして、お腹の調子を良好にしていくれるということで、最近お腹の調子が良くない主人や、乳製品を嫌う3才の娘にもいいのでは!と思い今回『オリゴのおかげ』を使ってみました。使い方は、とても簡単です。コーヒー紅茶など飲料に砂糖の代わりに入れて飲んだり、ヨーグルトや、トーストにかけても美味しいそうです。私は、煮物や卵焼きにいれたりしてオリゴ糖を取り入れています。毎日、スプーン3杯を続けていくことがポイントだそうです。忙しいときは、そのままスプーンですくって...
投稿日時:2011/07/23 : ![]() いいものみつけた♪
いいものみつけた♪

『オリゴのおかげ』モニプラ支店ファンサイト応援中お店で売っているのは知ってたんだけど、なんせいろんな種類の砂糖を持っていて勿体ないので・・・・...
投稿日時:2011/07/23 : ![]() ポチッとショッ...
ポチッとショッ...



こちらもモニプラさんから届きました♪“オリゴのおかげ”です見た事ありますよね?私も見た事あったし、聞いた事あったんですがオリゴ糖ってそもそもなんだっけ?という感じでした^^;そこでパンフレットに色々説明が書いてあったので載せてみます! おなかの性格を左右するのは、おなかのなかの「ビフィズス菌」でした。私達の健康や美容に役立つ領内善玉菌の代表が「ビフィズス菌」です。このビフィズス菌には不規則な食生活などで低下した腸の「ぜん動運動」を促しお腹を素直に変える働きがあります。ところが!このビフィズス菌はとってもデ...
投稿日時:2011/07/22 : ![]() 子育てママのお...
子育てママのお...

昨日から涼しいです。昨晩も結構寒かった。あいかわらずよく寝る毎日です、、10時前にに寝て、、朝3時に起きて夕飯の片づけたり、、あれ~~?ジョギングは台風のおかげで二日坊主で終わっています。今日も陽射しは強いのですが、部屋に入ってくる風が冷たい。。エアコンみたい、、オリゴのおかげを使ってみました!自然な甘さにほっとします。砂糖を紅茶にたくさんいれる、娘のために、、でも娘とお茶をするのが大好きなので、やめれないから、、オリゴのおかげで砂糖たちです。「オリゴのおかげ」のご紹介。「オリゴのおかげ」は、おなかの中にいる自分自...
投稿日時:2011/07/22 : ![]() 若返りの法則
若返りの法則

モニプラさんで「オリゴのおかげ」がモニター当選しましたスーパーではよく見かけるお品ですが実際使ったことがなかったのでワクワクしながらお試しお試しです~まずはそのままペロっと舐めてみる・・「あ、美味しい」甘すぎなくてさらっとしているからそのままでもペロペロいけるなぁ次は紅茶に溶かしてごくっと一口・・「癒される~」普通に美味しい紅茶です^^甘いものが大好きでしかもこれで整腸作用があるならこんな嬉しいことはないですカロリーも気にしなくていいしいままで食わず嫌いだった自分がオバカサンぜひリピートして続けたいと思います゚+.ヽ(≧...
投稿日時:2011/07/22 : ![]() ことちゃん、あ...
ことちゃん、あ...

最近意識して摂るようにしているのがオリゴのおかげ牛乳に含まれる乳糖とサトウキビなどに含まれるショ糖を原料にして酵素や酵母を使って作られたオリゴ糖ですカロリーはお砂糖の約半分で、毎日続けることでお腹の中のビフィズス菌を増やしていくことができるんだそうな。。。1日あたりの摂取推奨量はティースプーンで2杯と少しでいいのでコーヒーや紅茶に入れて飲んでいますシロップタイプなので冷たいアイスティーにもよく溶けますレシピ集も頂いたので、今度利用してみようと思いますが…今日は急遽、足りなくなったウナギのタレを自家製で作る際砂糖...
投稿日時:2011/07/21 : ![]() はにぱかのブログ
はにぱかのブログ
 .
2023.5.17.
.
おいしくなってきたトマトと新玉ねぎをたっぷり使ったラタトゥユ🍅
トマトのリコピンには抗酸化作用がたっぷり含まれているので、いろいろ気になっちゃうこの時期に免疫アップのお助け常備菜。
.
温めなくてもおいしいので、忙しい我が家の朝にぴったりで、暑くなるといつも常備しちゃってます。
.
今回はモニプラさんのモニターで当選したオリゴのおかげを使っておいしく仕上がりました🙌
.
トマトの酸味をまろやかにしてくれて、リキッドタイプなので片手で使いやすいし、混ざりやすい👏
.
ヨーグルトにも使って、腸活にも加勢してくれそうで、これからも期待して使っていこうと思います♡
.
息子のアレルギーチェックのかたゆで卵を食べ続けてはや数ヶ月…クリアできる日が待ち遠しいなー
.
#オリゴのおかげ #オリゴ糖 #パールエース #免疫力アップレシピ #春の食材 #オリジナルレシピ #monipla #oligo_fan #パン活 #パンが好き #ラタトゥユ #トマトレシピ #新玉ねぎ #新玉ねぎレシピ #野菜レシピ #おうちごはん #あさごぱん #あさごはんプレート #ワンプレートごはん #ワンプレート朝ごはん
.
2023.5.17.
.
おいしくなってきたトマトと新玉ねぎをたっぷり使ったラタトゥユ🍅
トマトのリコピンには抗酸化作用がたっぷり含まれているので、いろいろ気になっちゃうこの時期に免疫アップのお助け常備菜。
.
温めなくてもおいしいので、忙しい我が家の朝にぴったりで、暑くなるといつも常備しちゃってます。
.
今回はモニプラさんのモニターで当選したオリゴのおかげを使っておいしく仕上がりました🙌
.
トマトの酸味をまろやかにしてくれて、リキッドタイプなので片手で使いやすいし、混ざりやすい👏
.
ヨーグルトにも使って、腸活にも加勢してくれそうで、これからも期待して使っていこうと思います♡
.
息子のアレルギーチェックのかたゆで卵を食べ続けてはや数ヶ月…クリアできる日が待ち遠しいなー
.
#オリゴのおかげ #オリゴ糖 #パールエース #免疫力アップレシピ #春の食材 #オリジナルレシピ #monipla #oligo_fan #パン活 #パンが好き #ラタトゥユ #トマトレシピ #新玉ねぎ #新玉ねぎレシピ #野菜レシピ #おうちごはん #あさごぱん #あさごはんプレート #ワンプレートごはん #ワンプレート朝ごはん
 mamaライター★☆あるりん
✒︎
プルコギキンパ作ってみた♪
お肉を甘辛く炒める時に使ったのは『オリゴのおかげ』300g(シロップタイプ)✨
中の具材のたまご焼きにもオリゴのおかげを入れてほんのり甘くしました。
キンパにしたら子供達がお野菜沢山食べられるから不思議!!
オリゴのおかげは腸内環境を整えてくれるし、お料理にも使いやすいしおすすめ!
次男は便秘がちなので、朝作るバナナジュースにちょろっと入れて、お腹の調子を整えています(^^)
#オリゴのおかげ #オリゴ糖 #パールエース #免疫力アップレシピ #春の食材 #オリジナルレシピ #monipla #oligo_fan
#キンパ
#おうちごはん
#子供と料理
#今日の夕飯
#キンパ作り #ママご飯
#フレッシュジュース
#ミキサー
#バナナジュース
#followme
mamaライター★☆あるりん
✒︎
プルコギキンパ作ってみた♪
お肉を甘辛く炒める時に使ったのは『オリゴのおかげ』300g(シロップタイプ)✨
中の具材のたまご焼きにもオリゴのおかげを入れてほんのり甘くしました。
キンパにしたら子供達がお野菜沢山食べられるから不思議!!
オリゴのおかげは腸内環境を整えてくれるし、お料理にも使いやすいしおすすめ!
次男は便秘がちなので、朝作るバナナジュースにちょろっと入れて、お腹の調子を整えています(^^)
#オリゴのおかげ #オリゴ糖 #パールエース #免疫力アップレシピ #春の食材 #オリジナルレシピ #monipla #oligo_fan
#キンパ
#おうちごはん
#子供と料理
#今日の夕飯
#キンパ作り #ママご飯
#フレッシュジュース
#ミキサー
#バナナジュース
#followme
 鈴木 生久良
ずっと気になってた【オリゴのおかげ】✨
砂糖の代わりにお料理に使うだけで善玉菌の栄養となる「オリゴ糖」を摂り入れて腸内環境を整えてくれるの◟́◞̀♡
さっそく使ってみたよー♫
◆たけのこの甘辛焼
たけのこを油を引いたフライパンで軽く焼いて、醤油&オリゴのおかげ&隠し味に昆布茶&鰹節だけというシンプルな味付け✔️
土佐煮も美味しいけどちょっと味変したいにも🙆♀️
◆春キャベツと豚肉の味噌炒め
ごま油を引いたフライパンでキャベツと豚肉炒めて、火が通ったら味噌、オリゴのおかげ、酒、みりんで味付け👆
砂糖の代わりにつかうだけだから、筑前煮など何にでも使える♡
お料理だけじゃなくてコーヒーや紅茶に入れてもいいしヨーグルトやフルーツにかけてもいいね🥰
これなら手軽に腸活できるわ😄
#オリゴのおかげ #オリゴ糖 #パールエース #免疫力アップレシピ #春の食材 #オリジナルレシピ #monipla #oligo_fan #pr
鈴木 生久良
ずっと気になってた【オリゴのおかげ】✨
砂糖の代わりにお料理に使うだけで善玉菌の栄養となる「オリゴ糖」を摂り入れて腸内環境を整えてくれるの◟́◞̀♡
さっそく使ってみたよー♫
◆たけのこの甘辛焼
たけのこを油を引いたフライパンで軽く焼いて、醤油&オリゴのおかげ&隠し味に昆布茶&鰹節だけというシンプルな味付け✔️
土佐煮も美味しいけどちょっと味変したいにも🙆♀️
◆春キャベツと豚肉の味噌炒め
ごま油を引いたフライパンでキャベツと豚肉炒めて、火が通ったら味噌、オリゴのおかげ、酒、みりんで味付け👆
砂糖の代わりにつかうだけだから、筑前煮など何にでも使える♡
お料理だけじゃなくてコーヒーや紅茶に入れてもいいしヨーグルトやフルーツにかけてもいいね🥰
これなら手軽に腸活できるわ😄
#オリゴのおかげ #オリゴ糖 #パールエース #免疫力アップレシピ #春の食材 #オリジナルレシピ #monipla #oligo_fan #pr
 なんちゃましまし
お腹の調子を保つために善玉菌を増やして悪玉菌を抑える
オリゴ糖を摂りいれて腸内環境を整えて腸内フローラを育てる
オリゴのおかげは毎日の食事で手軽に家族の健康のお手伝いをしてくれるプレバイオティクス食品です
今回はオリゴのおかげを使って春の食材で免疫力アップレシピに挑戦しました🤗
先日長野旅行へ行った際親戚から これでもかと言うくらいのニラをたくさんいただき ニラチヂミを作ってみました
採れたてで柔らかく扱いやすい
隠し味にオリゴのおかげを入れて キムチの辛味やニラのニオイがマイルドに
チヂミにたっぷり入れて美味しく頂きました
ゴボウきんぴらの味付けにも
料理に飲料に
砂糖と同じように使えるので便利です
#オリゴのおかげ
#オリゴ糖
#パールエース
#免疫力アップレシピ
#春の食材
#オリジナルレシピ
#monipla
#oligo_fan
なんちゃましまし
お腹の調子を保つために善玉菌を増やして悪玉菌を抑える
オリゴ糖を摂りいれて腸内環境を整えて腸内フローラを育てる
オリゴのおかげは毎日の食事で手軽に家族の健康のお手伝いをしてくれるプレバイオティクス食品です
今回はオリゴのおかげを使って春の食材で免疫力アップレシピに挑戦しました🤗
先日長野旅行へ行った際親戚から これでもかと言うくらいのニラをたくさんいただき ニラチヂミを作ってみました
採れたてで柔らかく扱いやすい
隠し味にオリゴのおかげを入れて キムチの辛味やニラのニオイがマイルドに
チヂミにたっぷり入れて美味しく頂きました
ゴボウきんぴらの味付けにも
料理に飲料に
砂糖と同じように使えるので便利です
#オリゴのおかげ
#オリゴ糖
#パールエース
#免疫力アップレシピ
#春の食材
#オリジナルレシピ
#monipla
#oligo_fan
 ki2_cat
「オリゴのおかげ」をお試しさせて頂きました🥄◝✩
オリゴのおかげは、
ビフィズス菌の餌になるプレバイオティクス食品。
それならやっぱりヨーグルトに合わせるのが1番でしょ!と思い、
ヨーグルトにかけました。
体温ほどに温めたプレーンヨーグルト(冷たいと身体が冷えるので)に、
・バナナ(冷凍していたので色が黒い…)
・パイナップル
を入れ、上からオリゴのおかげを2回し。
上下混ぜて、いただきます🙏
ん〜!美味しい♥️(*´ч`*)
砂糖よりマイルドな甘さ。
液状だから、溶け残りが無く
ヨーグルトとよく混ざります。
ヨーグルト×オリゴのおかげ
の効果が私にはてきめんなのか、
翌日の便通はスッキリです✨️
便通のためはもちろん、
免疫を司る腸内環境のために、
今後も続けていきたいです!
#オリゴのおかげ #オリゴ糖 #パールエース #免疫力アップレシピ #春の食材 #オリジナルレシピ #monipla #oligo_fan
ki2_cat
「オリゴのおかげ」をお試しさせて頂きました🥄◝✩
オリゴのおかげは、
ビフィズス菌の餌になるプレバイオティクス食品。
それならやっぱりヨーグルトに合わせるのが1番でしょ!と思い、
ヨーグルトにかけました。
体温ほどに温めたプレーンヨーグルト(冷たいと身体が冷えるので)に、
・バナナ(冷凍していたので色が黒い…)
・パイナップル
を入れ、上からオリゴのおかげを2回し。
上下混ぜて、いただきます🙏
ん〜!美味しい♥️(*´ч`*)
砂糖よりマイルドな甘さ。
液状だから、溶け残りが無く
ヨーグルトとよく混ざります。
ヨーグルト×オリゴのおかげ
の効果が私にはてきめんなのか、
翌日の便通はスッキリです✨️
便通のためはもちろん、
免疫を司る腸内環境のために、
今後も続けていきたいです!
#オリゴのおかげ #オリゴ糖 #パールエース #免疫力アップレシピ #春の食材 #オリジナルレシピ #monipla #oligo_fan
特定保健用食品 『オリゴのおかげ』300g(シロップタイプ)
本物のトクホのオリゴ糖の効果を、是非皆さんのおなかで実感してください!
【許可表示:乳果オリゴ糖を主成分とし、腸内のビフィズス菌を適正に増やして、おなかの調子を良好に保つと食品です】という表示が許可された甘味料です。
摂取上の注意
●摂り過ぎあるいは体質・体調によりお腹がゆるくなることがあります。
●多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。